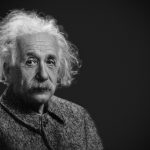「今度の休みに陶芸教室に行ってみようかな」「手打ち蕎麦を覚えてみたい」「カメラを始めてみようか」。
そんな風に思いながらも、結局「やってみたい」のまま時間だけが過ぎていく。
あるいは一度は体験してみたものの、気がつけば道具が押し入れの奥に眠っている。
そんな経験はありませんか?
実は博報堂生活総研の最新調査によると、「趣味にかける時間を増やしたい」と答えた人は56.7%にも上る一方で[1]、「趣味はない」と答える人が近年急増しているという現実があります。
多くの方が趣味への憧れを抱きながらも、なかなか続けられずにいるのです。
私は出版社でライフスタイル誌の編集を20年続けてきましたが、40代に入るまで実は「本当の趣味」と呼べるものがありませんでした。
仕事に忙殺される30代を経て、ふとしたきっかけで始めた手打ち蕎麦とジャズ。
この2つが、私に「続ける喜び」を教えてくれました。
趣味は一度始めたら終わらせてはいけないものではありません。
自分のペースで育てていくもの、そして何度でも再開していいものです。
この記事では、私が編集者として多くの趣味人を取材し、自身の体験も重ねて見つけた「趣味を続けるための3つの工夫」をお伝えします。
あなたの「やってみたい」を、「続いていてよかった」に変えるヒントがきっと見つかるはずです。
続かない理由を知る
趣味を続けるコツを知る前に、なぜ私たちは趣味を続けることが難しいと感じるのでしょうか。
取材を通じて見えてきた「続かない理由」を整理してみましょう。
「時間がない」は本当か?
「時間がない」は、趣味を諦める理由の第一位です。
確かに仕事や家事、子育てに追われる毎日で、趣味の時間を捻出するのは簡単ではありません。
しかし、本当に時間がないのでしょうか?
私が手打ち蕎麦を始めた頃を振り返ると、最初は「週末にまとまった時間がないと無理」と思い込んでいました。
でも実際は、平日の朝30分早く起きて蕎麦粉を捏ねる、帰宅後に包丁の手入れをする、そんな「細切れの時間」でも充分に趣味を楽しめることに気づいたのです。
「まとまった時間を確保してから始める」のではなく、「今ある時間の中で始める」
この発想の転換が、継続への第一歩になります。
初期投資へのためらい
「道具を揃えるのにお金がかかりそう」
これも趣味を始める際の大きなハードルです。
確かに本格的な道具は高価ですが、最初から完璧を求める必要はありません。
ジャズを始めた時、私は中古のキーボードから始めました。
音質は決して良くありませんでしたが、指使いを覚え、楽譜を読めるようになるには十分でした。
半年ほど続けてから、少しずつ機材をグレードアップしていく。
道具は「続けるための投資」ではなく、「続けた結果の自分へのご褒美」と考えると、無理のない範囲で楽しめます。
モチベーションの波と向き合う
「最初はやる気満々だったのに、だんだん面倒になって…」
これは誰もが経験することです。
心理学の研究によると、人間の行動の約45%は習慣で成り立っているとされています[2]。
つまり、モチベーションに頼るのではなく、「習慣化」こそが継続の鍵なのです。
やる気があるときだけ取り組むのではなく、
やる気がないときでも自然に手が動く状態を作る。
それが趣味を続ける秘訣です。
習慣化には21日から66日間が必要と言われています[2]。
最初の2ヶ月は「習慣作りの期間」と割り切って、完璧を求めすぎないことが大切です。
工夫1:日常に”趣味の居場所”をつくる
趣味を続ける最初の工夫は、物理的・時間的な「居場所」を作ることです。
専用の部屋がなくても、工夫次第で素敵な趣味空間は生まれます。
スペース・時間を「確保」から「習慣」に
私の知人で革細工を続けている方は、ダイニングテーブルの一角に小さな工具箱を置いているだけです。
食事の後片付けが終わると、自然とその場所に座って革を触る。
特別な「確保」ではなく、日常の「流れ」の中に趣味を溶け込ませる
これが続けやすさの秘訣です。
時間も同様です。
「土曜日の午後2時間」と決めるより、「夕食後の片付けが終わったら30分」の方が習慣になりやすい。
生活のリズムに合わせて趣味の時間を設計することで、無理なく続けられます。
【趣味の居場所作りのポイント】
- 道具の定位置を決める:使いたいときにすぐ取り出せる
- 片付けが簡単:準備と片付けに時間をかけすぎない
- 家族の動線を考慮:邪魔にならない場所を選ぶ
- 光と風通し:集中できる環境を整える
道具や場所への愛着を育てる
趣味を続ける人に共通するのは、道具や作業場所への深い愛着です。
私の蕎麦打ち道具は決して高級品ではありませんが、使い込むうちに手に馴染み、今では相棒のような存在になりました。
まな板の木目、包丁の重さ、打ち台の感触。
そうした道具との「対話」が、趣味の時間をより豊かにしてくれます。
場所への愛着も大切です。
窓際の小さなデスク、ベランダの一角、玄関先のガーデニングスペース。
どんなに小さくても、「ここが私の場所」と思える空間があると、自然とその場所に向かう足取りが軽やかになります。
家族との共有が生む”続けやすさ”
家族で楽しむ趣味の調査では、ゲーム、スポーツ、スポーツ観戦が上位にランクインしています[3]。
家族と趣味を共有することで、継続のモチベーションが格段に高まります。
私のジャズも、最初は一人で楽しんでいましたが、妻が「聴いているのが好き」と言ってくれてから、練習がより楽しくなりました。
家族全員が同じ趣味を持つ必要はありません。
一人が楽しむ姿を家族が応援してくれる、それだけで十分な「共有」です。
- 作品や成果を家族に見せる
- 趣味の話を食事の時にする
- 時には一緒に体験してもらう
- 趣味仲間を家に招いて紹介する
こうした小さな共有が、趣味を続ける大きな支えになります。
工夫2:小さな成果と仲間が支えになる
趣味を続ける二つ目の工夫は、「小さな成果」を大切にし、「仲間」とのつながりを育むことです。
「完成」より「継続」を楽しむ視点
趣味を始めると、つい「上達」や「完成」を目標にしがちです。
しかし、続けている人ほど「過程」を楽しむのが上手です。
手打ち蕎麦で言えば、最初は太さもバラバラ、切れ切れの麺でした。
でも「今日は昨日より少し細く切れた」「水回しの感覚が分かってきた」。
そんな小さな変化に気づき、喜べるかどうかが継続の分かれ道です。
ジャズでも、一曲完璧に弾けるようになることより、「今日は新しいコードを覚えた」「少しだけスムーズに指が動いた」という日々の小さな成長を大切にしています。
【小さな成果を見つけるコツ】
- 写真で記録する:作品や練習風景を撮って変化を確認
- 日記をつける:その日気づいたことを簡単にメモ
- 数値化する:練習時間、完成個数など測れるものは記録
- 比較する:一ヶ月前、一年前の自分と比べる
SNS・サークル・地域活動で仲間を見つける
一人で続ける趣味も素敵ですが、仲間がいるとモチベーションは格段に上がります。
SNSで同じ趣味の人とつながったり、地域のサークルに参加したり、趣味の教室に通ったり。
仲間との出会いが、趣味を「孤独な作業」から「楽しい交流」に変えてくれます。
私もジャズを始めてから、地域の社会人バンドに参加するようになりました。
上手な人の演奏を間近で聞けるだけでなく、「今度一緒にこの曲やりませんか?」と声をかけてもらえることが、練習への大きな動機になっています。
「一人でも楽しい、でも仲間がいるともっと楽しい」
これが趣味の理想的な状態です。
SNSでは、作品や過程を投稿することで応援してもらえたり、アドバイスをもらえたりします。
リアルでの交流が難しい場合でも、オンラインで仲間を見つけることは十分可能です。
続けることで変わる”自分への信頼感”
趣味を続けていると、技術的な上達以外にも大きな変化があります。
「自分は続けられる人間だ」という信頼感です。
これは仕事や家庭生活にも良い影響を与えます。
何か新しいことに挑戦するとき、「以前も趣味を続けられたから、これもきっと大丈夫」と思えるようになる。
小さな成功体験の積み重ねが、人生全体への自信につながっていくのです。
私自身、手打ち蕎麦を3年続けたことで、「継続する力」への確信が生まれました。
その後、ジャズやワイン、家庭菜園など、新しい趣味にも積極的に挑戦できるようになったのは、この自信があったからです。
工夫3:四季のリズムと趣味を重ねる
日本の美しい四季を趣味に取り入れることで、一年を通じて新鮮な楽しみを見つけられます。
季節ごとに変化する楽しみ方
日本では季節の変化を日常生活に取り入れる文化があります[3]。
趣味も同じように、季節ごとに楽しみ方を変えてみましょう。
例えば、私の手打ち蕎麦は季節によってこんな風に変化します:
【四季の蕎麦打ち】
- 春:新蕎麦の季節。香り高い蕎麦粉で季節を感じる
- 夏:冷たいざる蕎麦。涼を呼ぶ薬味を工夫する
- 秋:温かいかけ蕎麦。きのこや根菜の出汁を楽しむ
- 冬:年越し蕎麦の準備。一年の締めくくりとして
ガーデニングなら春の種まき、夏の世話、秋の収穫、冬の計画。
読書なら春は新生活本、夏は冒険小説、秋は哲学書、冬は古典。
同じ趣味でも季節ごとにテーマを変えることで、マンネリを防げます。
イベントや記念日をきっかけに
日本の年中行事を趣味のきっかけにするのも効果的です。
正月、節分、ひな祭り、端午の節句、七夕、お盆、お月見、クリスマス。
こうした節目を「趣味の発表会」や「新しい挑戦のタイミング」として活用してみましょう。
私は毎年大晦日に、一年間練習したジャズの曲を家族の前で演奏する「家族コンサート」を開いています。
小さなイベントですが、「今年はこの曲を完成させよう」という目標ができ、練習に張り合いが生まれます。
【季節イベントと趣味の組み合わせ例】
- 料理:おせち、桜餅、冷やし中華、月見団子など季節料理に挑戦
- 手芸:クリスマスの飾り物、お雛様の小物、浴衣の帯など
- 写真:桜、花火、紅葉、雪景色など季節の被写体を追う
- 音楽:春の歌、夏祭りの曲、秋の調べ、冬の讃美歌など
季節感が趣味のモチベーションになる理由
なぜ季節を取り入れると趣味が続きやすくなるのでしょうか。
それは、「時の流れ」と「成長の実感」が結びつくからです。
「去年の今頃はまだ始めたばかりだったな」「桜が咲く頃には、きっとこれができるようになっているだろう」。
季節の循環と自分の成長を重ね合わせることで、趣味に深い意味と継続の動機が生まれます。
また、日本では「初」を大切にする文化があります[3]。
初桜、初雪、初詣。
「今年初めての○○」という特別感が、趣味に取り組む気持ちを新鮮に保ってくれるのです。
四季の移ろいとともに深まる趣味は、
単なる技術習得を超えて、
人生を豊かにする「季節の友」となってくれます。
まとめ
趣味を続けるための3つの工夫をご紹介してきました。
1. 日常に”趣味の居場所”をつくる
- 完璧な環境を待たず、今ある空間と時間を活用する
- 道具や場所への愛着を育む
- 家族との小さな共有を大切にする
2. 小さな成果と仲間が支えになる
- 完成よりも継続、結果よりも過程を楽しむ
- SNSやサークルで仲間とつながる
- 続けることで育つ自分への信頼感を味わう
3. 四季のリズムと趣味を重ねる
- 季節ごとに楽しみ方を変えてマンネリを防ぐ
- 年中行事をきっかけに新しい挑戦をする
- 時の流れと成長を重ね合わせて深い意味を見つける
趣味は「一度始めたら終わらせてはいけないもの」ではありません。
「自分のペースで育てていくもの」「何度でも再開していいもの」です。
40代で趣味を再発見した私が、編集者として多くの趣味人を見てきて確信していることがあります。
それは、趣味を続けることで得られるのは技術や知識だけではないということです。
季節の移ろいを感じる心、小さな変化に気づく観察力、仲間との温かなつながり、そして何より「自分らしい時間」を大切にする生き方。
趣味は心の栄養であり、人生を豊かにする最良の投資です。
同じ40代の視点から趣味について発信されている森智宏さんの40歳から始める大人の趣味選びでも、アラフォー世代が生涯を通じて続けられる趣味の重要性について語られています。多くの専門家が共通して指摘するように、40代こそ新しい趣味を始める絶好のタイミングなのです。
あなたの「やってみたい」という気持ちを、ぜひ大切にしてください。
完璧を求めず、自分のペースで、季節とともに。
きっと、「続いていてよかった」と思える日が来るはずです。
そして時には、趣味を通じて出会った仲間や作品が、予想もしなかった人生の扉を開いてくれるかもしれません。
今日から、小さな一歩を踏み出してみませんか。
参考文献
[1] 博報堂生活総研「生活定点1992-2024」調査 [2] STUDY HACKER(スタディーハッカー)- モチベーションには頼らない。継続する人になるための「習慣化の技術」 [3] 識学総研 – モチベーション維持のためのたった1つのコツを解説最終更新日 2025年7月9日