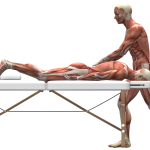1)ゼネラル・コントラクターと呼ばれるゼネコンのお仕事
世の中には一般的な名称のほかにも、さまざまな略称でよばれている会社がいくつかありますが、ゼネコンとされる大手の建設会社もそのひとつといえるでしょう。
そもそもゼネコンは英語でゼネラル・コントラクターと書いた場合の頭文字の綴りからとったもので、日本語で直訳すれば総合的な請負企業とでもいうべきものです。
したがってかならずしも建設界隈という意味自体が英語に含まれているわけではないのですが、実際のところわが国では地元にある中小の建設会社を超越した、日本全国あるいは世界を股にかけた活動をしている大手の建設会社の意味合いで使われるのが一般的なあり方といえるでしょう。
請負は他の個人や企業からの依頼により製品をつくり、完成したあとでその対価を受け取る形態のことをいいますが、ゼネコンが請負契約だけをしているのかといえば、こちらも決してそのようなことはなく、さらに幅広い事業活動を展開しています。
具体的な事業活動の分野ですが、建築関連であれば都市部の高層マンションやデパート、オフィスビルなどの多くがそうですし、これらの建物単体だけではなく、たとえばマンションとデパートなどが一体的に整備される街区全体を手掛けていることがあります。
建築というよりも都市開発の用語のほうが似合う分野です。
ほかにも民間だけではなく、たとえば市役所や都道府県庁・国の中央官庁などの庁舎整備、陸上競技場や体育館・運動公園などの大規模な公共施設の建設も含まれており、施工管理が厳密で期間や予算などの制約も民間よりもシビアな公共施設は、過去の実績や技術力も踏まえて、ゼネコンでなければならないできない仕事のひとつになっています。
もちろん最近では新規の建設工事以外にも、高度経済成長時代などの過去につくられた施設の改修工事その他のメンテナンスの分野でも主要な役目を果たすことがあります。
2)設計と施工が両方とも自社の内部で完結
このようにゼネコンの守備範囲は幅広い分野にまたがっているため、少なくとも同業他社を圧倒するほどの資本力があり、人材や営業拠点なども同様に社内的に蓄積されていることはひとつの条件と見てもよいといえます。
ある意味でいえば建設の世界での便利屋のような存在ですが、その役割を満たすためには設計と施工が両方とも自社の内部で完結できなければならず、装備と人材への投資は膨大なものがあります。
世界的に見れば設計と施工が別々の会社に分離して分業になっていないのはめずらしい形態といえますが、日本のゼネコンはこのような特徴こそが企業の強みです。
直接的には設計や施工には関連しないものの、防災面での対策強化や新製品の建材開発、施工手順の効率化などの観点から、社内的に独自の研究施設をもち、職務発明を特許や実用新案などとして登録している場合もあり、これらも財産のひとつといえます。
設計部門は単独の建築物の設計から都市計画までさまざまな規模がありますが、規模の大小は適用される法令などの規制の多さにも直結します。
東日本大震災を引き合いに出すまでもなく、わが国の国土は南北に細長い独特な形状で、気候条件なども南北ではかなり異なっているため、地震・台風・地すべり・津波などの自然災害は枚挙にいとまがないほど多くなっています。
そのようななかで安全かつ快適な住みよいまちづくりを目指すための工夫として、都市計画法・建築基準法・工場立地法・都市再開発法・土地区画整理法をはじめとするさまざまな法令がこれまでに制定されてきました。
これらの法令のさらに下位には省令や通達にもとづく技術的基準も多数存在しているほか、都道府県や市町村が定める条例規則や要綱もあります。
3)前田裕幸氏が考えるゼネコンに必要な能力とは
したがって単に設計とはいっても法令を知らなければ仕事ができず、しかも毎年条文が改正される場合もあるため、知識やデータ収集などの分野でも卓越した能力が求められています。
施工部門もプロジェクトが大掛かりになればなるほど、多くの予算と人員を投入し、あわせて国や自治体、地権者などの関係者間の連絡調整を図らなければなりませんので、その仕事量も膨大となります。
特に実際の施工の技術そのものもさることながら、工事期間中の進行管理などの実務的な部分での能力もなければなりません。
実は社内的には携帯ができるスマートフォン端末などを使ったオートメーション化なども進んでおり、効率性をできるだけ追い求めながら顧客が必要とするサービスを提供する側面においても、他の建設会社と比較して一歩先んじた存在になっています。
そして顧客からの要望にしたがって特定の建築物を建築する業務だけではなく、みずからベッドタウンの住宅団地、あるいは駅前の分譲マンションなどの開発を企画し、施工する場合もあり得ます。
この場合は施工の段階だけにとどまらず、分譲後の建物の日常的な管理や保守点検、大規模修繕工事の施工などの運営やメンテナンスの部分にも大きく関与することがあり、将来の収益のあり方を示す一端にもなっています。
最終更新日 2025年7月9日