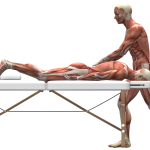健康食品のOEMについて
健康食品のOEMは非常に効率よく商品を作ることができるとして多くの食品メーカーで行われています。
高齢化が進み健康に対する意識が高まっている現代においては、健康食品は非常に重要の多い商材であり、通常の食品に比べて継続して購入される可能性が非常に高いため、食品メーカーにとっては非常に高い利益が見込める商品となるのです。
しかし多くの大手食品メーカーは健康食品に対する知識が乏しく、またその生産体制も整っていないことが少なくありません。
そこで健康食品を専門に製造しているメーカーに製造を委託し、 OEM供給をしてもらうことで自社製品として販売していることが多いのです。
OEMは現代社会では一般的に行われている製造方法です。
食品に限らず大手の製造メーカーでは様々な種類の製品を販売していますが、そのほとんどは自社ではなく外部の企業の工場に委託して製造を行っているものが多いのです。
この方法を選択することで、自社で製造する際の設備投資や管理コストを抑え、効率よく製品を製造することができるようになります。
また特殊な製品については販売数量もそれほど多くないため、大手メーカーのような大規模に製品を製造する会社では生産体制や管理体制がそぐわないことも少なくありません。
その際にOEMの手法を利用することで、自社で設備投資をすることなく少量多品種の製造が可能となり、効率よく商品を販売することができます。
製造コストを大幅に削減することも可能
さらにこの方法を利用することで製造コストを大幅に削減することも可能になります。
近年では人件費の問題が大きくそのコストを圧迫していることがよく知られており、その人件費を軽減するために海外に工場を設立し現地で製造した製品を日本に輸入することで効率の良い商品の製造を行う会社が増えています。
海外の現地の安い労働力を効率的に利用することで、国内で製造した場合に比べて大幅な人件費の低減が可能となるため、競争の激しい世界においては価格の低減や利益の向上など様々な面でのメリットが大きいものです。
ただしこの体制についてはいくつか注意しなければいけない点があります。
1つは商品の品質をどのようにして確保するかという点です。
大手食品メーカーの多くは健康食品に関する知識が乏しいため製品がどの程度の品質を維持しているのか、またそのリスクはどの程度あるのかについて統計的に判断する手法がありません。
そのため製造元のメーカーの経験を頼りに製造しているケースが多いのですが、製造元のメーカーによっては、自社の利益を追求するあまり粗悪な材料を使ったり、きちんとした製造工程を経ずに製造しているケースも多いのです。
そのため本来であれば第三者の健康食品に詳しい期間のチェックを受け、食品として問題がないことを立証してから販売しなければいけないのですが、この検査を行うためにはその人件費がかかるため、コストを下げるために全数検査を教えず野球危険性に切り替えたり、最悪の場合には全く検査をせずに販売をしている場合もあるので注意が必要です。
販売者の注意点
また、販売元のメーカーには中小企業が多く、客観的なマーケティング能力や商品のプロデュース能力が乏しい場合も少なくありません。
しかし大手メーカーにもこれらの食品に関するノウハウがないため十分なマーケティングをせずに商品を販売してしまうことも多いのです。
この場合商社の要求を十分に汲み取ることができずに発売してしまうため、商品の売れ行きが著しく悪かったり、商品の価値を認めてもらえないと言ったことが起こる危険性もあります。
そのため大手メーカー側ではOEM委託をする前に事前に十分なマーケット調査をし、その結果を踏まえて充分な商品の価値を提供することができる会社に製造を依頼することが重要になります。
さらに食品のOEMについては販売者として充分に注意しなければいけない点があります。
それは健康被害のリスクです。
通常の商品の場合には外観や実際の商品で粗悪なものであるかどうかがわかることが多いのですが、食品の場合にはその内容を確認することができず、品質の問題など様々な問題が発生してしまう危険を持っています。
特に外部委託先が小さな企業であった場合、商品販売の実績がないためつの品質が十分に確保されていなかったり、指定通りに商品が納入されなかったりといった問題を発生することが多く、また本社と取引先で規定している様々な条件をよく知らないために取引先に対して多大な迷惑をかけてしまうということが少なくありません。
都心は政治的な関連により様々な業務が決められることも多いため、結果として依頼元の大手メーカーに対してトラブルを引き起こすことも少なくないのです。
食品製造の外部委託については万が一の場合には健康被害を伴うため非常にその基準が厳しくなっています。
販売者だけではなく製造者の連絡先もラベルに記載することが義務付けられているほか様々な制約があります。
最終更新日 2025年7月9日