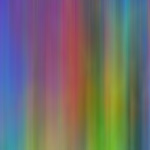「ゼッチの導入を考えているがメリットが知りたい」
「ゼッチ住宅を建てる際の注意点は?」
「株式会社エスコシステムズさんにZEH住宅の相談を考えている」
近年では注文住宅を建てるにあたり、ゼッチを導入するか検討する家庭が非常に増えてきています。
新たな住まいの形として注目を集めているものですが、導入することによってどのようなメリットがありデメリットがあるのか、また注意点等についてしっかりと把握しておくことが求められます。
* 平均年収660万円×社員の約8割が既婚者 *
エスコシステムズで「ゆとりある幸せな暮らし」、はじめませんか?
→株式会社エスコシステムズの採用・求人情報
目次
ゼッチとは?
近年建築や住宅の分野においてゼッチという言葉をよく耳にしますが、一体どのようなものなのか説明できる人は少ないかもしれません。
環境にやさしいのはもちろんのこと、快適で安心して住むことができる環境を作り出すことができる住宅として注目がなされていて、国内の多くのエネルギー問題を改善するために、現在では国も推進している政策に当たります。
ネットゼロエネルギーハウスの略称であり、住宅の断熱性能や省エネ性能などを挙げ、さらには太陽光発電など生活に必要となるエネルギーを自分の過程で作り出すことで、年間の消費エネルギー量を出来る限り0以下にする住宅のことを指しています。
ゼッチ住宅に設定されている条件
そもそもどのような条件が設定されているのかと言うと、断熱性能、省エネ性能、そして創エネの3つの要素が必要となっています。
それぞれにクリアしなければならない基準が設定されているため、それらもしっかりと頭に入れておく必要があるでしょう。
断熱性能
まず最初に断熱性能とは、室内の外に熱を伝えにくくする性能のことを表しています。
断熱性能に優れていると、夏の熱い外気を室内に伝えることなく、反対に冬は室内の暖かさを外部に逃すことがないので、冷暖房にかかる費用を削減しながら、年中快適に過ごすことができるでしょう。
省エネ性能
そして省エネ性能については、現在の消費量を従来よりも20%以上を削減することが求められているのです。
その中でも特にエネルギー消費が大きいとされている空調と照明、給湯と換気の4つの項目においては、基準を満たしている機器を使わなければなりません。
創エネ
創エネはエネルギーを作り出すことを指していますが、太陽光発電をメインに、家庭用燃料電池、蓄電池なども上手に活用した上で導入することが求められます。
日常的なエネルギー消費だけではなく、災害の際の補充にも役立てられることでしょう。
きっかけは2011年に発生した東日本大震災
なぜこのような取り組みが行われているのかと言うと、そのきっかけにもなったものが2011年に発生した東日本大震災です。
災害の多い日本にとって、エネルギー自給率が低い事は大きな問題とも言えるでしょう。
災害が発生するたびに日本国内のエネルギー生産が間に合わなくなって、エネルギーの価格が不安定になる可能性が大いに考えられると言うことです。
ゼッチを普及させることで、エネルギー需給構造の改善が期待されています。
ゼッチを導入するメリット
健康に対して良い影響が期待できる
ゼッチを導入することにはメリットがありますが、その1つが健康に対して良い影響が期待できる点です。
断熱性能が高くなれば、住宅の中の温度差が小さくなります。
血圧の変動や体温調整が少なくなることで、体調改善にも大きくつながることでしょう。
光熱費の削減にも大きくつながる
そして光熱費の削減にも大きくつながります。
住宅自体が断熱性能が上がるので、冷暖房をそれほど使用することなく快適な室温を保つことが可能です。
夏や冬においては、光熱費の面でも大幅な削減が見込めるでしょう。
災害時でも安心して生活することができる
また災害時でも安心して生活することができます。
太陽光発電と蓄電池を合わせて取り入れることにより、日光が出ている時間であれば常にエネルギーを作り出すことができ、蓄えも可能です。
災害の際には停電になることも多いですが、このような場合にも蓄えたエネルギーで必要な機器を動かすことができるため安心です。
快適性の向上し、住宅の価値も上がるとされています。
ゼッチを導入するにあたっての注意点
しかしゼッチを導入するにあたり注意点があるのも実情です。
建設費用が高くなる
その1つが建設費用が高くなる点です。
条件を満たすためには基準をクリアした設備を導入しなければならず、太陽光パネルや蓄電池、エアコンなどの機器など、多くの面でコストがかかります。
このようなことから、全体の建築費用も高くなることが予想されます。
必ずゼロになるわけでは無い
またゼッチを導入したからといって、必ず0になるわけでは無いことを覚えておかなければなりません。
空調や給湯、照明や換気等の一次消費エネルギーだけでゼロにすることができますが、その他の消費分はこれに含まれていないのです。
住宅の消費エネルギーを太陽光発電、蓄電池などを使い全てを賄いたいと考えている場合にはかなり無理があることがわかります。
補助金の支給項目や金額には十分な注意が必要
また補助金の支給項目や金額には十分な注意が必要です。
支給の項目、金額等はその年により大きく変化しています。
2020年、2030年までに目標を達成しようと考えていることから、その前後において補助金の支給がなくなる可能性も大いに考えられるでしょう。
まとめ
導入するにあたり、その年の補助金の支給状況などをしっかり確認した上で、どれぐらいの建築コストがかかるのか、設備内容などもしっかりと比較検討することが求められます。
最終更新日 2025年7月9日