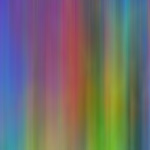1,天災が多い国だから備える意識を持てた
日本の建築物の耐震性能が高いのは国民の意識が高いからと考えていいでしょう。
勿論、職人さんの技術が高いという事はありますが、国民全体が耐震性能の重要性を認識していて、これを求めるという事をしている事も大きな要因として考える事が出来ます。
そのために、日本は天災が多い国でありながら、比較的大きな天災が起きにくい国になったといえます。
これは、技術が凄いという事はあるのですが、国民の一人一人の意識が高いので、大きな天災にならないように備えているという事も大きな要因と考える事が出来ます。
つまり、国レベルで天災に備える意識が大きな意味を持っているというわけです。
これは、他の国と比較してみるとよくわかります。
他の国では地震が起きた時に考えられないような大きな被害になってしまうという事があります。
地震の大きさは震度というもので表現されるのですが、日本では比較的あるぐらいの震度のものであっても、それが他の国からすれば想定外もいいところの震度なので、あっという間に建物が崩壊して大事故になってしまうという事があるわけです。
基本的に地震というものに備えるという意識がない所もあるという事。
この事は、ある意味では地震が起きることが極めて少ないわけですから、良い事になるのですが、ちょっとした地震で壊滅的にダメージを受けるという事では、リスクは高いというように考えてもいいかもしれません。
ですから、天災に関して、安全な国ほど実は安全ではないという事も言えるのかもしれないのです。
2,天災被害に警戒し対応できてきている日本
日本はそういう意味では常に警戒をしていることで、安全ではないにしても、被害が少ないように出来るという意味で、リスクは低くなっていると考えてもいいかも知れません。
天災が頻繁に起きるという事を上手く自分達の生活に取り入れたと考えてもいいかもしれない。
何しろ地球は一つでつながつているわけですから、ある所で頻繁に起きることが、別の所ではほとんど無いといっても、絶対に同じ事が起きないなどと言える事ではありません。
地球の規模からすれば、ちょっとしたくしゃみをすれば、それが地震となって至る所に出てくる事は考えられることでしょう。
それに備えないというのは極めて危険だと考えるしかありません。
ですが、この考え方というのは一朝一夕で出来るような事ではありません。
人は出来るだけ楽をしたいと考えるので、起きるのかどうか分からないものに備えるというのは極めて苦手という事もいえるのです。
日本人ぐらい天災に対してひどい体験をしていれば、それが当然ということにも考えられるのですが、日頃ほとんど天災が無いというような国ではまずこうした考え方は出て来ないでしょう。
それがこの問題の難しい所ということになるわけです。
3,国と国民が天災への意識共有が出来ている
今は技術などはインターネットでいくらでも仕入れることが出来ますし、天災が世界各国で起きているという事は世界中の人が知っているという事になりますが、その事を自分にも起こり得ることとして考える事が出来るのは、そうした経験を持っている人だけという事にもなってしまいます。
その意識を変えるという事が難しいのが、その耐震などに備える考えたの難しい所でしょう。
いざ備えるという事になればどの程度の備えをするのかという事を考えなければなりませんし、まず様々なことで問題が起きることは想像が出来ます。
まずは設備や施設は全てある程度以上の耐震性能を持つというような法律から制定していくということになるのでしょうが、これについて根拠が求められることにもなるはず。
そうなると、なかなか進まなくなるというのが目に見えています。
日本はそういう意味ではある程度の天災が起きるということで、意識を共有することが出来ていて、恵まれたというようにも考える事が出来るのかもしれません。
自治体が避難訓練をするといえば、それに人が集まるぐらいですから、その意識の高さは極めてハイレベルと考えていいでしょう。
民間で運営されるボランティアによる活動なども活発にありますから、こうした事を考えてもこの国の意識の高さというのが伺えます。
これがあることで災害からのダメージがより少なくなっているという事は間違いないでしょう。
被害をゼロにするという事は出来ませんが、被害を少なくするという事に関しては、出来ない事はないわけです。
この意識があるのかどうかでまず大きな違いという事になりますし、意識があれば、さまざまなところで同じ考え方で行動を共にすることが出来る人が増えていくことになります。
避難訓練をするという時にもこうした人達が活躍するのは当然の事でしょう。
ですから、㈱キーマンも強く言及してますが、日本は世界に誇る防災システムを持っているという事にもなっているわけです。
参考サイト:㈱キーマンは耐震技術のプロフェッショナル
最終更新日 2025年7月9日